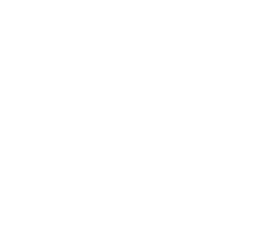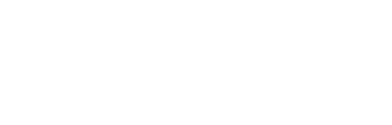薬学用語解説
パーキンソン病
作成日: 2023年07月22日
更新日: 2024年03月01日
薬理系薬学部会
© 公益社団法人日本薬学会
ジェームズ・パーキンソンが1817年に初めて報告した、振戦、筋固縮、無動、姿勢保持障害を4大主徴とした進行性神経変性疾患。く、わが国では10万人に50~100人、50代後半の発症が多い。初発症状は手足のこわばり、ふるえ、歩行障害であり、日常のすべての動作が遅くなり、表情が乏しく、声が小さく聞き取りにくくなり、次第に転びやすくなる。これらの症状があって、それがパーキンソン病薬の服用により著しく改善されることでパーキンソン病と診断される。 薬物療法の中心はレボドパ、ドパミンアゴニスト、B型モノアミンオキシダーゼ (MAO-B) 阻害薬である。レボドパはドパミンの前駆物質であり、パーキンソン病のほとんどの症状に対して劇的な効果があるが、効果の持続する時間が比較的短く、また数年服用し続けると作用時間がさらに短くなる、一日の中で体の動きの良いとき悪いときの差が大きくなる,体が自分の意志に反して動いたりこわばったりする(ジスキネジー、ジストニー)などの問題が起こる。ドパミンアゴニストはレボドパと比べると作用時間が長く、症状の日内変動を軽減できる。精神症状発現リスクが高い/当面の症状改善を優先させる特別な事情がある/運動合併症のリスクが低い、のいずれかに該当すればレボドパで治療を開始し、これらの条件いずれにも該当しない場合はドパミンアゴニスト、もしくはドパミンの分解を抑制するMAO-B阻害薬を選択する。