活薬のひと
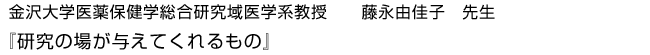

私は、北海道大学薬学部を卒業後、札幌医科大学博士課程を経て、岡山大学医学部、米国ハーバード大学Children’s hospital 病院、大阪大学微生物病研究所、そして金沢大学医学系と、図らずもいろいろな大学・研究施設で研究を学びそして実践してきました。今回『活薬のひと』へ投稿する機会を頂きまして、それぞれの場が私の研究に与えてくれたものについて、振り返ってみることに致します。
私の研究生活は、北海道大学薬学部薬効学教室で宇井理生教授の下で行った、百日咳菌毒素を用いた細胞内情報伝達系の研究に始まります。その後はウイルス関連の仕事で博士課程(札幌医科大学がん研究所分子生物学部門)を修了し、岡山大学医学部細菌学教室(小熊惠二教授)で助手の職を得てボツリヌス菌の産生する神経毒素(ボツリヌス毒素)の研究に携わることになりました。今から思い返すと、宇井研究室で『毒素のおもしろみ』を知ることができたこと、そして一流の成果(GTP結合タンパク質Giの発見)を生み出した研究室が持つ『研究の流儀』が20代前半の若者であった私に、知らず知らずのうちに大きな影響を与えていたのだと思います。
さて、就職を機にボツリヌス毒素をテーマとすることになり、当時、私は、ボツリヌス菌が作り出す毒素がヒトを含めた様々な動物に多大な影響を及ぼすという現象を、分子レベルで解明していくことにとても興味を覚えました。しかし、岡山大学に赴任したその年に、イタリアやドイツのグループがボツリヌス毒素の神経における標的分子を立て続けにNature誌などに掲載し、これでは勝ち目がないということで、私はあまり注目されていない毒素に付随する無毒成分の構造と機能の解析を行うことになりました。このような地味とも言える研究が8年ほど続きましたが、あまり焦ることもなく、じっくり研究対象に向き合えたのは、岡山大学医学部の助手という安定感のある職を得ていたことがよい方向に働いたとのだと思います。その後の米国留学は、学内の公募がきっかけでした。ラボの選択は、ボスであるDr. Lencerの書いた論文の派手ではないが論理的で過不足のない考察をする『作風』に憧れて決めました。Lencer先生のラボにお世話になった二年半の間には、コレラ毒素の細胞内輸送機構についてまとまった成果をあげることができました。また、Lencer先生は論文から感じられたとおりの誠実な人柄で、お手本となるボスに巡り会えたということも大きな収穫でした。帰国後、アメリカで学んだ上皮細胞の細胞生物学研究の新しい手法で、再びボツリヌスの仕事をしてみたところ、例のボツリヌス毒素に付随する無毒成分に、だれも予想していなかった特異的で強力な生物活性(上皮細胞の細胞間バリアを可逆的に破壊する活性)があることに気がつきました。その発見を面白いと思ってくださった大阪大学微生物病研究所の目加田英輔教授にお世話になり、2004年より同研究所に研究の場を得ることができました。大阪大学では、他分野の先生方との共同研究で、ワクチン開発、組織工学や再生医療への応用など、毒素研究の枠を超えて新しい研究プロジェクトに参加する機会もでてきました。これらの研究の中には、従来の専門分野の枠組みの中では発想すらできなかったものがあり、そこからは特に面白い成果がでてきています。
これまでの私の経験を振り返ってみると、『研究の深さ』と枠にとらわれない『自由な機会(気持ち)』があれば、その研究はいつかきっとすばらしい発見や、強力なものを生み出すことに繋がるという気が致します。『研究の深さ』とは、研究対象を深く探求し誰も知り得なかった新しいことを知るという意味です。この作業は研究者にとって醍醐味でありますが、一見役に立つようには見えないことであったり、その研究対象は他の人が注目しないような地味なものであったりもします。しかし、そのような研究を、『自由な機会(気持ち)』で展開することにより、予想外の非常に革新的な成果を生むことがあります。私の場合、じっくりとその研究対象に取り組み追求する『深さ』は、北大薬学時代に宇井先生をはじめ、教官だった先生方の真摯に研究に取り組む姿をみることができたことと、岡山大学時代に幸運にも助手となり研究に専念できたことから得られました。そして閉鎖的ではない『自由な機会(気持ち)』は異なるバックグランドを持つ多くの優秀で活発な研究者が集まり、異分野間の情報交換の機会が多い大阪大学という場から得られたと思います。現在、私はラボを運営する立場になり、今度は私が若い研究者達にこれらの恩恵を与えることが役目になってきました。若い研究者達の地道な研究や斬新な研究を見出し、彼らにその芽をじっくりのばせる研究環境を与えることが、研究者として多くの時間を過ごさせていただいてきた私の次の目標です。一方、現実は厳しく、現在の若い研究者は、博士課程を修了後すぐに安定した研究職につけることはほとんどなく、2〜3年といった短い任期の博士研究員となる場合がほとんどです。そこで、サバイバルを強いられるという環境が『知の深さ』を追求する楽しさを若者から奪っているようにも感じます。これでは、大きな可能性を持った若くて優秀な人材がなかなか集まりません。大阪大学では私自身、任期つきの特任教授として教室を運営し、ポスドクたちと一緒に、将来への不安感と自由度の高さの両方を味わいました。その後、2015年8月より金沢大学医学系細菌学教室の担当教授として赴任しました。今度は任期がなく安定ではありますが、研究に加えて教育や運営の仕事もたくさんあります。そしてラボをおく場は研究所から医学系(部)へと大きく変わりました。これを機会に、今までの細菌毒素を中心とした研究に加えて、医学部だからやりやすいこと、例えば疫学的な研究など新しい風を入れるとともに、じっくりと時間をかけた研究を展開したいと思っています。
最後になりますが、今後、より多くの若者が、世界で一番の『深み』を目指して研究に没頭し、そして柔軟な発想力の源である『自由な機会(気持ち)』を育む環境が、大学や研究所などの研究の場で調えられることは、日本の生命科学研究を推し進めるために益々大切になると痛感しています。
過去の記事
- 日本薬学教育学会世話人/昭和大学薬学部教授 中村明弘 先生 『サイエンスとしての“薬学教育学”の確立を目指して』
- 日本製薬工業協会 会長 畑中好彦 氏 『創薬イノベーションへの挑戦』
- 日本大学薬学部 教授 亀井美和子先生 『これからの医療と地域の薬剤師の関わり方』
- 国立民族学博物館/総合研究大学院大学 教授 鈴木七美 先生 『スイスにおける養生文化とエイジ・フレンドリー・コミュニティ』
- ファルメディコ株式会社 代表取締役社長 狭間研至先生 『薬剤師が変われば、地域医療が変わる』
- 熊本大学大学院薬学教育部教授 甲斐広文 先生 『運を運びたければ足を運べ』
- 東北大学加齢医学研究所教授 高井俊行 先生 『薬学とスマート・エイジング』
- 東京大学大学院医学系研究科医学教育国際研究センター 講師 孫大輔 先生 『家庭医の私と薬学』
- 神戸大学医学部附属病院薬剤部長 平井みどり先生 『くすりを輝かせるために、薬剤師は何をすればいいか』
- NPO法人患者スピーカーバンク 理事長 鈴木信行 氏 『患者と医療者が共に、誰もが輝く社会をめざす』
- 株式会社ファルマデザイン 代表取締役社長 古谷利夫 氏 『改めてゲノム創薬への期待』
- 内閣府食品安全委員会委員長代理 山添康 先生 『化学物質の安全性と薬学』
- 日本製薬工業協会 会長 多田正世 氏 『新薬創製への挑戦』
- 日本薬剤師会 新会長 山本信夫 先生 『薬剤師の活動を支える薬学』
- 日本プロセス化学会 会長 富岡清 先生 『有機化学徒、プロセス化学に出会う』
- アジア薬科大学・薬学部協会 専務理事 菅家甫子 先生 『躍動するアジアの薬学教育ハーモナイゼーション』