活薬のひと
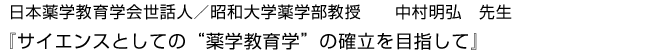

平成28年8月27日、日本薬学教育学会(英文名Japan Society for Pharmaceutical Education、略称JSPhE)が誕生しました。日本薬学会にはかつて薬学教育改革大学人会議や薬学教育部会があり、現在は薬学教育委員会が教育に関する活動の主体となっています。“薬学教育”を冠する団体としては、薬学教育協議会、薬学教育評価機構があり、日本薬剤師会と日本病院薬剤師会には薬学教育委員会が設置されています。これらはいずれも薬学教育を対象とした活動を行う組織です。一方、このたび設立された日本薬学教育学会は初めて“薬学教育学”を掲げた学術団体です。日本薬学教育学会は、学術集会の開催、学会誌の発行、国内外の関連団体との交流及び協力などの事業を通して、薬学教育研究に携わる会員の情報発信・共有の場を提供し、サイエンスとしての“薬学教育学”の確立、薬学教育に関する研究の充実発展並びにその成果の普及を目指します。
日本薬学教育学会と現在活動中の薬学教育に関連した団体や委員会との違いについて尋ねられることがありますので、以下に現時点での活動方針を紹介させていただきます。
この10余年に及ぶ薬学教育改革において薬学教育関係者は、薬学教育モデル・コアカリキュラム、薬学共用試験、実務実習、薬学教育第三者評価など、新たな教育システムを構築してきました。これらの過程においては、各団体等に設けられた委員会によって原案が策定され、また全国からの意見のとりまとめにはワークショップやパブリックコメントなどの手法が用いられてきました。これらのプロセスの詳細については、日本薬学教育学会から発行予定の書籍「薬学教育6年制のあゆみ」(アークメディア刊)を是非ご一読ください。
6年制薬学教育課程がスタートして10余年が経ち、新たな教育システムは円滑に運用されるようになってきています。そこで重要となるのが、薬学教育改革の成果の検証です。果たしてこの間の薬学教育改革は有効で所定の成果を収めることができているのでしょうか。教育は個々の教員の個人的な考えや経験に基づいて実践されていることが多いように思います。この状況は医療においてevidence-based medicineが提唱される前の“経験に基づく医療”とよく似た状況です。薬学教育にも科学的根拠が必要であり、evidence-based pharmaceutical educationを実践すべきときがきています。
一方、これまで薬学教育関係者は新たな教育システムの構築と実践に精一杯で、教育に対する科学的なアプローチを推進する取り組みは乏しかったといえます。これからサイエンスとしての“薬学教育学”を普及し確立していくためには、薬学教育を対象とした学術活動を支援・促進するための組織が必要であり、このたびの日本薬学教育学会の設立に至りました。つまり、日本薬学教育学会の活動方針は、委員会活動によって教育システムの構築や提言を行うことを目指すのではなく、薬学教育を対象とした研究活動を支援促進し、研究成果の発表の場を提供することにあります。また、教育実践研究など新たな領域の研究活動も支援してまいります。誕生したばかりの学会ですので、その活動は会員が主体的に考案し実践することを目指しています。「日本薬学教育学会」の学術活動、すなわち学術集会の開催や学会誌「薬学教育」(Japanese Journal of Pharmaceutical Education:JJPhE)の発行などを通して、薬学教育に関する研究成果や実践報告の発表の機会を提供することは、薬学教育のサイエンスとしてのレベル向上につながるものと確信しています。
幸いにして、日本薬学教育学会の第1回大会参加者は予想をはるかに超える約600名となりました。参加者は大学教員だけでなく、学生、病院・薬局の薬剤師、企業の研修担当者など、薬学に関する教育に関わる多様な立場の方々にご参加いただきました。まさに、これが日本薬学教育学会の目指すところです。日本薬学教育学会という名称から大学教員が主体となる学会のように思われがちです。しかし、薬学教育は大学教育で完結するものではありません。大学は薬学教育のスタートであり、その後、どのような進路を選択しても生涯にわたって学習と研鑽は必須です。大学教職員をはじめ、薬剤師、学生(学部、大学院)、病院・薬局・企業の教育研修担当者など、広く薬学の教育に関わる者が本学会に参集し、薬学教育に関する学術活動を展開していくことを期待しています。個人会員、学生会員だけでなく、機関会員や賛助会員も募集していますので、大学、病院、薬局、企業単位での入会も可能です。詳しくは日本薬学教育学会のホームページあるいはFacebookをご覧ください。
日本薬学会は薬学教育モデル・コアカリキュラムの策定・改訂をはじめ、薬学教育改革において常に中心的な役割を果たしてきました。現在も薬学教育委員会が中心となって文部科学省委託事業やワークショップなど、薬学教育の改善・充実に資する活動を積極的に行っています。一方、日本薬学教育学会は誕生したばかりで、まずは学会誌「薬学教育」の発行と学術集会の開催を堅実に実行する体制の整備から取り組んでまいります。日本薬学教育学会としては、薬学教育を対象とした研究の振興を通して薬学教育のサイエンスとしてのレベルの向上・発展に貢献し、日本薬学会をはじめ他の教育関連団体と連携し、それぞれの役割においてともに発展していければと考えております。学会の運営と活動が軌道にのるまでしばらく時間がかかると思いますので、成長を温かく見守っていただき、ご指導ご助言をよろしくお願い申し上げます。
過去の記事
- 日本製薬工業協会 会長 畑中好彦 氏 『創薬イノベーションへの挑戦』
- 日本大学薬学部 教授 亀井美和子先生 『これからの医療と地域の薬剤師の関わり方』
- 国立民族学博物館/総合研究大学院大学 教授 鈴木七美 先生 『スイスにおける養生文化とエイジ・フレンドリー・コミュニティ』
- ファルメディコ株式会社 代表取締役社長 狭間研至先生 『薬剤師が変われば、地域医療が変わる』
- 熊本大学大学院薬学教育部教授 甲斐広文 先生 『運を運びたければ足を運べ』
- 東北大学加齢医学研究所教授 高井俊行 先生 『薬学とスマート・エイジング』
- 東京大学大学院医学系研究科医学教育国際研究センター 講師 孫大輔 先生 『家庭医の私と薬学』
- 神戸大学医学部附属病院薬剤部長 平井みどり先生 『くすりを輝かせるために、薬剤師は何をすればいいか』
- NPO法人患者スピーカーバンク 理事長 鈴木信行 氏 『患者と医療者が共に、誰もが輝く社会をめざす』
- 株式会社ファルマデザイン 代表取締役社長 古谷利夫 氏 『改めてゲノム創薬への期待』
- 内閣府食品安全委員会委員長代理 山添康 先生 『化学物質の安全性と薬学』
- 日本製薬工業協会 会長 多田正世 氏 『新薬創製への挑戦』
- 日本薬剤師会 新会長 山本信夫 先生 『薬剤師の活動を支える薬学』
- 日本プロセス化学会 会長 富岡清 先生 『有機化学徒、プロセス化学に出会う』
- アジア薬科大学・薬学部協会 専務理事 菅家甫子 先生 『躍動するアジアの薬学教育ハーモナイゼーション』