薬学と私 第36回
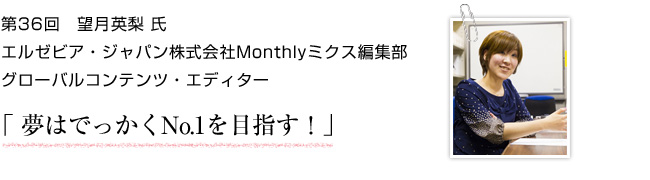
「薬とか医療について書く仕事に就けたらいいな。医療って魔法みたいでカッコイイもん!」。そう思ったのは、小学校低学年くらいの頃だっただろうか。幸か不幸か、私が抱いた最初で唯一の夢だ。きっかけとなったのは、薬剤師が出てくる1冊の児童書、柏葉幸子さんの「地下室からの不思議な旅」という本を手にとったことだ。主人公のアカネが薬局を営むチィおばさんとともに、異世界を旅するファンタジー。異世界では薬剤師は錬金術師だ。作者の柏葉さんが薬剤師であることもあるのかもしれないが、物語の中に出てくる薬の話にも惹かれた。子供心に医療は魔法みたいでカッコいい!と憧れた。
当時、祖母が糖尿病の末期で、病院で透析を受けつつも自宅で療養していた影響もあったのかもしれない。普段水を飲むことすらできず、喉が渇くと、「英梨ちゃん、氷取ってきて…」と頼まれる。そんな毎日を過ごす祖母も透析を受けた後は、すこぶる調子が良かった。医療のことはカケラも分からなかったが、大好きな祖母を健康にしてくれるもの。それが私にとっての医療だった。
私はいま、海外学会などを中心とした医療・医学界、そして製薬企業の取材を中心とした取材活動、編集業務を担当している。幸運なことに小さい頃の夢がかなったわけだが、天邪鬼な私は、最初は、違う仕事に就いた。しかし、思い描くようにいかない。現実に追われるうちに、いつしか夢や仕事への情熱も忘れ、自分への自信もなくしていった。
そんなある日、勤務していた製薬企業の上司、同僚と飲みに出かけた。普段は寡黙な上司がなぜか仕事について熱く語り、最後にこう言った。「チャンスはそんなに多くはない。もし、本当に自分にやりたいことがあるのならば、チャンスが来たら他人を押しのけてでも絶対に取りなさい」と驚いた。当時の私は、自分が欲しくても誰かが欲しいと言えば喜んで譲るタイプだったのだから。
その夜、インターネットを見ていた私は、毎日目を通していた製薬業界向け業界紙が記者を募集していることを知った。応募書類だけでなく、辞表まで書きあげてしまったのは、やはりアルコールが抜けきっていなかったのだろう。後から記者経験がある人を募集していたことを知って青くなった。いまも「自分にできるだろうか…」と迷うと、この言葉を思い出す。見かけによらず実は小心者の私の背中を押してくれた当時の上司には、今も感謝の念に堪えない。
1か月後、晴れて記者になった。職場は、活気があると言えば聞こえはよいが、とにかくうるさい。原稿をめぐって喧嘩をしている者がいる横で、わき目も振らずに原稿を書いている者がいる。そうかと思えば、原稿を書き終わったのか、スポーツ紙に夢中になっている者もいる。これは今もあまり変わらないが、締切までに原稿を書けば、あまり口うるさく言われることはない。これが私の仕事の特権だと勝手に思っている。
仕事が終われば、呑みに出かける。最初に皆が「ビール大ジョッキ2杯」と口を揃えて注文することもさることながら、仕事が終わったばかりなのにもかかわらず皆が熱い議論を交わすことに驚いた。テーマはきまって、“業界記者としてのジャーナリズム”。自分の意見で皆を説得できないと怒られる。とんでもないところに就職してしまったと思った。しかし、デパート業界の業界紙編集長だった椎名誠の私小説「銀座のカラス」の世界が実際にあったのかと勝手に憧れてしまった。実際、仕事に全力で情熱をかけられる先輩記者たちの姿はカッコよかった。何を間違ったのか、いつか自分の視点で自分の言葉で何か伝えられるようになりたいと、一人前になるまで何があっても頑張る、と決めてしまった。
当時、女性記者は少なく、バリバリの体育会系。基本的に先輩が言うことに対し、“NO”ということは許されない。入社三年目までは、通称“芋洗い”。皆が執筆したい1面や独自記事(=料理)は先輩記者、それ以外のプレスリリースなどの仕事(=芋洗い)は、後輩記者が執筆する。毎日が料理を作るための修業というわけだ。言われたことは何でもやった。
しかし、本当に仕事ができず、失敗の連続だった。同期の中でも、一番出来が悪かったと思う。超有名製薬企業の名称の表記を間違えたり、締切を忘れて取材に出かけたり、編集長の編集方針に根拠もなく逆らったり・・・いま考えると真っ青なミスの連続。編集長からは毎日のように怒鳴られ、時に真剣に説教され、そのたびに取材の資料や原稿が宙を舞った。泣きべそをかくことは毎日のようにあったけれど、不思議なことに辞めたいと思ったことはなかったし、仕事は大好きだった。いまの私があるのは、この頃の編集長の教えのお陰だといまは思う。
出来の悪かった私を記者、編集者として育ててくれたのは、海外学会での取材経験だ。それまで私は取材とは取材者に教えてもらい、勉強するものだと思っていた。しかし、海外のジャーナリストは違った。例え一般紙に所属していても、専門的な知識を取得するために、日ごろから勉強するのは当然のことで、プロ意識をもって取材者とディスカッションを行っていた。専門的な知識を身につけることは、何が正しい情報か判断するのを助けてくるだけでなく、原稿の質の高さにもつながる。海外のジャーナリストから、専門性を身につけることの重要性を学んだ。
英語でインタビュー、取材させていただくと、日本人ではまだ珍しいようでラッキーと思うことも少なくない。記者会見で質問した後に、「good question!」と話しかけられたり、一度お会いした医師、製薬企業の方に覚えてもらっていたり…。だが、グローバル化が進む中にあって、躊躇しているのは日本人だけなのかもしれない。多くのアジア人ジャーナリストは流暢な英語を操る。日本のメディアは、日本語という壁に守られている分、グローバル基準になりきれず、成熟しきっていないのかもしれない。
いま懸念されている、臨床研究のデータ改ざん問題について、Monthlyミクスでは、サイエンスの観点に着目した。臨床研究に携わる医師側の知識不足、責任感の欠如という観点から一石を投じさせていただいた。医療界、製薬業界の両方を取材する立場で何ができるのか、かなり悩んだが、最後はこれまで取材している間に培われた(?)専門性が記事に少しでもにじみ出ていたら嬉しい限りだ。
海外学会を取材する中で、日本の情報をグローバル基準で世界に発信する、という新しい目標もできた。一時は夢がなく、この仕事に就いた時も一人前になれるかさえ不安だったことを考えると、我ながら、まぁなんとビッグな夢を抱くようになったものだと驚く。そう思わせてくれるのは、これまでの仕事で出会った多くの方々のおかげだ。傍から見れば回り道に見えるほかの職種を経験したことも、その場で学んだことは大きかったし、何より尊敬する方々に会えたことを感謝している。
いまの私の座右の銘は、“ナンバーワンになれ!”だ。私がいまだに上司の編集長から怒られると口酸っぱく言われる言葉でもある。超怠け者で、いつも勝手にあきらめてしまう私には耳の痛い言葉だ。人を蹴落とすという意味にも捉えられがちだが、編集長によると「本当のナンバーワンになれば、周囲は気にならないはず」ということらしい。自分がまだまだであることを教えてくれるとともに、また明日もう少し頑張ろうと思わせてくれる言葉だ。
地域医療が推進される中で、薬剤師の担う役割はますます重要になっていくことが予測される。国が“医療と介護の一体提供”を重要視し、今後はこれまでの病院などの“施設完結型”から“地域完結型”へシフトすることが求められている。薬剤師も地域に出向くことが求められる中で、薬剤師への期待も大きい。是非、薬局や病院薬剤部などの施設から一歩外に踏み出して、地域に目を向けてほしいと思う。今後の薬剤師の役割の変化には、ひとりのジャーナリストとして注目している。