薬学と私 第3回
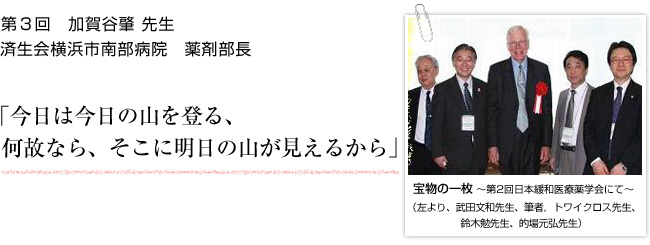

私の父は、秋田鉱山専門学校(秋田大学鉱山学部:現工学資源学部の前身校)の出身で、家には鉄鉱石の原石などのサンプルがたくさんあり、そうした父のコレクションの原石を手にするうち、地学やサイエンスに興味を抱くようになりました。
中学生になり、自分の将来を考えた時、地学や工学もいいがもっと人と関われる「白衣を着る仕事をしたい」と思うようになりました
そして、大学進学となった時、サイエンスへの興味と「将来白衣を着る仕事をしたい」という希望が融合し、明治薬科大学に進学しました

当時は、医療薬学の授業などなく、基礎薬学中心で、それらを学んでも、どこか物足りなく、 「この先に自分のやりたいことがあるのか?どのような仕事があるのだろう?」という疑問がいつもありました。
4年生となり、2週間の病院実習(国立東京第二病院:現東京医療センター)に行きました。そこで目にした光景、自分の体験は衝撃的なものでした。大学で学んだ薬学の知識が、院内特殊製剤として医療現場で薬剤師から具現化されて提供されていることに感激しました。
「これまで学んだことは、世のため人のために意味のあることなんだ!!」
そして、そこで働く人たちは,皆自分の仕事に誇りを持ち、真摯に取り組んでいました。その姿を目の当たりにし、医療現場で働くことに魅力を感じ、病院薬剤師となることを決心しました。

1975年に私が入職した北里大学病院は、「事を処してパイオニアたれ」という北里柴三郎博士の理念のもと、新しい医療を目指して、1971年に開院した病院です。患者中心の医療を皆で築こうという雰囲気が、病院全体に漲っていました。
子供の頃より、一番バッターが好きでした。一番バッターしか初球ホームランは打てませんからね(笑)。最初に踏み出す恐怖や不安はあるけれど、未知への興味の方が私には勝っていました。そんな私ですから、他の人が未だ踏み込んだことのない処に臆することなく、出向きたかったのです。
「臨床の場に、薬剤師も行かなければ!」と病院に入ったばかりの新人の頃から生意気にもそんなことを思い描いていました。
「調剤室に閉じこもり、受身でいるのでなく、もっと自発的に仕事ができないか?」
同じ志を持つ同期の新人薬剤師の仲間がいました。
薬品管理課に配属された新人の私と同志はまず医薬品管理を通して病棟に入り込もうと企てました。医師も看護師も病棟で私たちを歓迎してくれました。当時の薬剤部長の朝長文弥先生は病院薬剤業務の先駆者で、新しい病院薬剤業務のトレンドは北里大学病院が発信地だったと言っても過言でないくらい色々な新しい試みがなされました。
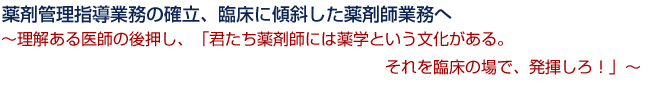
さらに、もっと薬学の知識を直接患者に活かせる業務をやりたいと思うようになりましたが、調剤中心の当時、どのようにしたらいいか道筋がつかめませんでした。しかし、当時臨床に導入され始めた中心静脈栄養法(IVH intravenous hyperalimentation)と長く携わった製剤業務がマッチしました。IVH業務は、物理化学、配合変化など製剤学の知識や技術、栄養学や生化学など、これまで学んだ薬学の知識を集約したような業務であり、薬剤師の活躍し処でした。こうして業務を積み重ねるうちに、医師たちは薬剤師を診療のパートナーとして頼りにしてくれるようになりました。
私たちだけでなく、全国にはすでに病棟に出向き、臨床業務に挑戦する病院薬剤師は少しずつ増えてきていました。もはや調剤室に閉じこもっている時代は終わっていたのです。
1987年、北里大学病院が厚生省のモデル病院となり現在の薬剤管理指導業務のプロトタイプを作ることになりました。私は朝長先生からそのプロジェクトのリーダーに任命され、臨床薬剤業務を開発することになりました。当時北里大学病院長の故坂上正道先生は、
「君たち薬剤師には薬学という文化がある。それを臨床の場に行って、思う存分発揮しろ!その文化を医者に伝えろ!そうでないとチーム医療は推進できない。」と言われ、私たちを応援してくれました。
私たちは、調剤、医薬品管理など物中心の業務から、医師とともに臨床にかかわる医療薬学を背景にした人中心の業務に転換を図りました。1988年、現在の薬剤管理指導業務(いわゆる100点業務)が診療報酬として新設されました。病院薬剤師の直接の患者サービスが、初めて診療報酬として評価されたのです。

病棟業務が薬剤管理指導業務として認められるようになりましたが、そこで私は悩みました。
「私たちはミニ医者ではない、どうしたらもっと臨床での薬剤師の仕事を理解してもらえるか」と。
病院に新医療技術導入機構プロジェクトが発足し、1989年、初めてのコメディカルの海外派遣者として、海外研修の機会が与えられました。この研修で私はミシガン大学病院とケンタッキー大学病院を研修先にしました。当時ミシガン大学薬学部副学長・薬剤部長であったDrデレオンとの出会いも大きいものでした。
私はクリニカルファーマシストの精神論的な話ではなく、具体的な業務のノウハウを学びました。
「臨床業務を成功させるためには、DI業務がしっかりしてないとダメ。」
「病棟での質問や対応を全て記録に取りなさい。でないとただの勉強で終わってしまう、これはビジネスだ。」
4ヶ月間の海外研修でしたが、私の薬剤師人生を大きく変えるものでした。

アメリカ研修から1年後、突然国際電話がかかってきました。
「私は麻酔科の的場といいます。今オハイオ大学で研修留学中です。
1年後に帰国したら、一緒に緩和医療の仕事をしましょう。チーム医療をやりましょう。」
1年後、帰国した麻酔科医に「なぜ私ですか?」と再度尋ねると、初対面の的場元弘先生(現国立がん研究センター中央病院緩和医療科・精神腫瘍科科長)は言いました。
「アメリカで私を助けてくれたのは、クリカルファーマシストでした。色々な考え方や知識を教えてくれたのは、彼らです。」
「私はチーム医療を行う上で、薬剤師を絶対外せないことを、身をもって体験しました。あなたは本場のクリニカルファーマシストから学んだことを私と一緒に実践してください。」
こうして私は、緩和医療の領域に足を踏み入れることになりました。緩和医療チームを発足させ、そこで10年間ともにチーム医療を実践し、的場先生から多くのことを学ばせてもらいました。
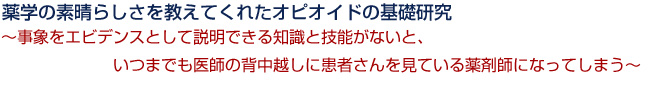
緩和医療の背景にある薬学は、これまでの製剤学的知識も必要でしたが、中心となるのは薬物治療学でした。しかも取り扱う薬剤はオピオイドが中心です。その薬理作用などをきちんと説明できるような知識と技能がないと、医療現場で薬剤師の専門性を発揮できないことを痛感しました。
緩和医療は臨床が先行することが多いのですが、それを基礎できちんと説明をつけてくれたのが、星薬科大学薬品毒性学教授の鈴木勉先生でした。依存や耐性のメカニズムや副作用発現用量についてなど鈴木先生の研究は、まさに臨床薬学であり、臨床現場の薬剤師を勇気づけ、薬学の素晴らしさを教えてくれるものです。
そして、2007年、鈴木先生を代表とし、病院薬剤師ばかりでなく、多くの薬局薬剤師、薬学研究者の賛同も得て、日本緩和医療薬学会を設立することができました。

1999年、済生会横浜市南部病院の薬剤部長に就任し現在に至ります。これも前任の薬剤部長平林哲郎先生のお誘いがあったからです。ここでも,優秀なスタッフや理解ある医師にめぐり会い、親密な医療スタッフとの交流から、大学病院のような大所帯では出来難いことを実現することができました。
2008年、病院薬剤部スタッフの多大な尽力を得て、第2回日本緩和医療薬学会年会の年会長となり、メインテーマを「緩和医療の知識・技能・態度をみがく」として開催することができました。
緩和医療に携わる者にとっては神様のような存在であるオックスフォード大学名誉教授のロバート・トワイクロス先生に、ダメもとで、講演依頼の手紙をしたためたところ、なんと「OK」の返事が来たのです。そして日本のWHO方式がん疼痛治療法の第一人者である武田文和先生に座長をお願いし特別講演が実現しました。パシフィコ横浜のメインホールは通路まで聴衆で埋め尽くされ、トワイクロス先生は、
「薬剤師が緩和医療にかかわり、2000人を超える聴衆が集まることは、想像を絶する、素晴らしいことだ!」
とおっしゃり、「がん患者の症状マネジメント」について感動的な講演をされました。この時、トワイクロス先生と武田先生たちと撮った写真は、私にとって生涯の宝物となった1枚です。
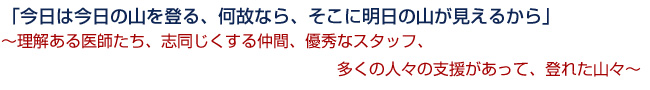
この言葉は、北里大学病院当時腎センター部長で私のアメリカ研修を後押ししてくれた酒井糾先生が、済生会横浜市南部病院に赴任する際に色紙に書いて下さった言葉です。私はこの言葉をいつも心においています。
「多くの山があるけれど、いきなり高い山を登るのではなく、まず目の前の山、自分が登れそうな山を登ってみる、頂上に立てば、別の景色が開ける。」
と思っていました。いくつの山を登っても、次に登るべき山がありました。そうして、これまでやってきたのが、私の人生だったと思います。
そして、いつも、どの山においても、薬剤師に理解ある医師にめぐり会い、看護師に助けられ、病院内外に志を同じくする多くの薬剤師の仲間がおりました。そして他のコメディカルや優秀なスタッフの協力がありました。多くの方々の支援があって、いくつもの山を登ることができました。とても幸せなことであり、改めて、これまで出会った方々に深く感謝致します。
そして、鉱山学を専門としながら、家業を継がなければならなかった亡父は、私の志を重んじ、応援してくれました。また物怖じしないように育てたのも、恐怖心なく一番バッターとして、未踏の山を登るのに功を奏し、両親にも改めて感謝致します。これらは家族の絆と応援・理解なくしてはありえなかったことと思っています。
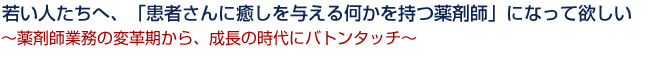
このように、私たちは、病院薬剤師の業務を、調剤室から病棟に拡げ、そして物中心の業務から人(患者)中心の業務に変革させてきました。変革ができたけれども、その質や環境を十分に整備するまでには至りませんでした。
そして、今はその業務の質を向上させ、体制整備し、さらに成長させる時代となりました。基礎薬学しかなかった私の頃の大学教育とは違い、医療薬学を学んだ若い薬剤師、そして長期の臨床実習を含む6年制教育を受けた薬剤師が活躍する時代です。調剤室、病棟、さらに薬局薬剤師と連携して、在宅に、業務が進展しています。
「臨床現場で、何か人のために役に立ちたい」と思う心、志、目的意識を、しっかり持って欲しいと思います。漠然と与えられた授業や実習をこなしていても、何の糧にもなりません。
「薬剤師として,医療、患者さんにどのように関わりたいか?」
学生時代から考えて欲しいと思います。
患者さんとの関わりには、「知識」や「技能」ばかりでなく、「態度」もとても重要です。緩和医療ばかりでなく、命や死に向き合わなければならない場面もあります。生や死、医療に対する自分の考えを持つことも必要です。臨床実習を通して、是非考えて欲しいと思います。
そして授業や医療現場で、もっと質問して下さい。質問し、皆で知識を共有し、ディスカッションを重ねることで、知識や技能は醸成され自分のものとなります。大学教育で学び、体験したすべての薬学を背景に、自分なりの「何か(Something else)」を持ち、「患者さんに癒しを与える何かを持つ薬剤師」
となって欲しいと思います。
私が、これまで多くの人々に後押ししてもらったように、これから若い薬剤師の山登りを後押しできればと思っています。