薬学と私 第20回
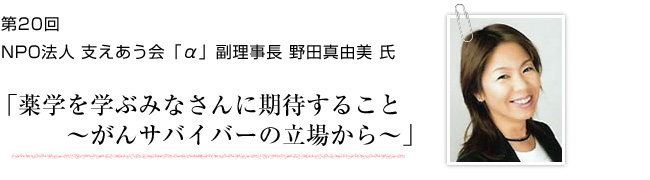
日本では、生涯のうちにがんになる可能性は、男性の2人に1人、女性の3人に1人と推測されています。がんは、決して特別な病気、珍しい病気ではなく、実はとても身近で、ありふれた病気だと言えます。誰もが、生涯のうち何らかの形でがんと関わることになる、と考えておく必要があるのかもしれませんが、実際は、なかなかそうはいきません。がんと告げられた時のことを多くの人は、「青天の霹靂」だったと言います。
1998年、私は、早期の乳がんと診断されました。がん告知を受けたときは、座っていた椅子がガタガタと音を立てるほど震えました。どんなに早期と言われても、「がんはがん」、私にとっては、命に関わる怖い病気でした。そして、死への怖れと同じくらい大きかったのが、治療そのものへの怖れでした。抗がん剤の副作用で苦しむ患者のイメージを自分に重ね、治療を怖れました。
実は、私は中学生時代、愛読書は「家庭の医学」というほど、医療に強い関心があり、医師になりたいと思ったこともあります。残念ながらまったく別の人生を歩いてきましたが、医療への関心が薄れたことはなく、がん医療の状況もある程度理解していたので、がんになったらどんな治療を受けたいかという自分なりの考えを持っていました。また、インターネットが一般家庭にも普及しはじめた時期でもあり、米国国立衛生研究所のがん情報を和訳して公開しているサイトにあった医療者向けの情報をセカンドオピニオン代わりにして、私は治療法を決めました。当時は、私のような患者はまだめずらしかったようです。幸い、抗がん剤治療は必要がなく、術後、ホルモン剤を服用しましたが、体の節々の痛みやこわばり、気持ちの不安定さや、気力のチャージができないなどの副作用は、どれも我慢できないほどではないものの、生活の質を落とす私には辛い治療でした。
私の手術が終わり、ほっとした矢先に、今度は父が余命3か月の膵がんと診断されました。67歳の父は、毎日10キロ以上のウォーキングを欠かさず、「俺は100まで生きるから覚悟しろ」とよく言っていました。告知はせず、積極的な治療ではなく症状緩和を中心に、できるだけ自宅で過ごすことを決めました。 父の病状は、幸いゆるやかに進行していきましたが、経口抗がん剤による味覚障害で食欲が落ちると一気に体力が低下しました。薬を中止し、近所の診療所で点滴を受け食欲の回復を待ちました。また、痛みのコントロールに苦労しました。NSAIDsとモルヒネの徐放剤を併用していましたが、病院には緩和医療の専門スタッフはおらず、がんのメーリングリストで緩和やがんの専門医、看護師、薬剤師の方からいただいたアドバイスを父の主治医に伝え幾度もモルヒネの増量を交渉しました。
11か月、父は、膵がんと静かに闘い、少し短い生涯を終えました。自分自身の乳がん体験、そして、父の闘病の記録をwebサイトにアップすると、たくさんの患者や家族から相談のメールや掲示板への書き込みがありました。医療について、がんについて、本当に何も知識がない、情報を得られない多くの人たちの声を聴くうち、少しでもそういった人たちのサポートをしたいと思い、2001年、支えあう会「α」というがん患者会に参加し、患者さんやご家族の支援活動を始めました。また、2006年からは、千葉県がんセンターの患者相談支援室に所属しがん相談業務に携わっています。
患者会や相談室では、さまざまながんの患者さんやご家族との出会いを経験します。患者や家族の悩みは多岐にわたりますが、その中でも多いのは“くすり”に関する悩みです。抗がん剤治療は、副作用を伴う厳しい治療です。制吐剤の進歩など、化学療法の副作用の辛さは緩和されてきましたが、それでも、皮膚障害や末梢神経障害など、患者の生活に大きな影響を与える副作用に苦しんでいる人が多くいます。また、外来化学療法の普及や、経口薬の進歩により、多くのがん治療が通院で行われる時代です。医療者に囲まれた入院環境とは違い、患者や家族は地域の中で大きな不安を抱えて暮らしています。指示通りに薬が飲めなかったとき、副作用かもと心配になったとき、身近な薬局に安心して相談できる薬剤師がいてくれたら私たちはどれほど心強いことでしょう
近年、新規抗がん剤や分子標的薬が次々に登場し、がんにおける薬物療法は、劇的に変わってきました。私の父の発病が今だったとしたら、何も治療しないという選択はおそらくありえなかったと思います。しかし、新しい薬が私たち患者の元に届くまでには長い時間と、いくつものハードルがあります。ヨーロッパでは、臨床試験のデザインから患者が関わっている国もあり、例えば「薬効はあるが、副作用で夜中に何度も目覚めてしまうような薬では困る」そんな意見が言えるのは患者自身だからこそだと言います。一方、日本では、新薬開発のプロセスや治験への正しい理解が進んでいるとはいえません。治験と聞くと人体実験と考えてしまう人もいれば、治験薬=夢の新薬、と思っている人もまだたくさんいます。残念ながら、がんをすべて治す薬はまだありませんが、新薬開発や治験がもっと速やかに進み、がんをコントロールしながら生きていける、そんな薬が早く届くことを私たちは待ち望んでいます。
2012年は、薬学部が6年制になってから初めての国家試験が行われ、6年間の教育を受けた薬剤師が現場に登場すると大きな注目をもって迎えられた年だと思います。みなさんは、自分の未来をどのように描いているでしょうか。患者さんの顔を見て言葉を交わしサポートする臨床薬剤師でしょうか。治験を行う医師や、治験を受ける患者をサポートするCRCでしょうか。画期的な新薬を開発し多くの人に希望を届ける研究者でしょうか。
「どんな」薬剤師になりたいのか、薬剤師として「何を」したいのか、それぞれの描く未来は違っていると思いますが、志を持ち、ビジョンを掲げ未来へ向かってほしいと思います。
みなさんが関わるのは患者や家族の人生です。ひとりひとりが、かけがえのない唯一の人生を歩いている「生活者」だということを心に留めて、プロ意識をもってそれぞれの「場」で活躍されることを期待し、エールを送ります。